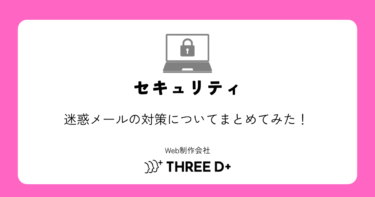多くの人が「毎回アクセスするたびにパスワードを思い出せず、結局再設定することになる」という経験を持っているのではないでしょうか。
本稿では、パスワードにまつわる対策や通説、技術の実態について、それぞれの課題とともに解説していきます。
パスワードは便利さと安全性を両立できているのか?
パスワードとは、あらかじめ設定した合言葉で本人確認を行う仕組みです。専門的には「記憶情報を使った認証方式」と呼ばれています。
パスワードはコストが低く、手軽な認証手段として、広く普及しています。特にコンピュータやインターネットとの親和性が高く、今やスタンダードな方法となっています。
しかし、ネットサービスの数が増え、日常のあらゆる場面でパスワードが求められるようになると、もはや記憶力だけで複数のパスワードを管理するのは困難です。アクセスのたびにパスワードを忘れ、再設定を繰り返したことがある方も多いでしょう。
スマートフォンやクラウドといった利便性の象徴である技術も、パスワード管理の煩雑さによって、その利便性が損なわれることがあります。
さらに問題なのは、パスワードは「それを知っていれば、誰でもアクセスできてしまう」という性質を持っていることです。これはセキュリティ対策として致命的なリスクを孕んでいます。
本来、利便性と安全性を両立するはずのパスワードが、むしろその両方を妨げる存在になっているのではないでしょうか。

パスワードの大規模流出はもはや日常茶飯事
ここ数年のサイバー攻撃の傾向を見ると、フィッシングメールによる「アカウント情報(IDとパスワード)」の詐取が顕著な問題となっています。
以前は、ハッキングやマルウェアによってシステムそのものに侵入する手法が主流でしたが、近年は手軽かつ効果的なフィッシング詐欺が主な手口となっています。
現在では、多くの業務システムや商用サービス、公共インフラがクラウド化されています。クラウドサーバーは高いセキュリティ下にありますが、そのぶん直接侵入は困難です。結果として、攻撃者は認証情報を抜き取ることに注力するようになっています。
大規模なアカウント情報の漏洩も、もはや珍しいものではありません。以下はその一例です:
-
Yahoo!(米国):2013年に30億件のアカウントが流出
-
Equifax:2017年に1億4800万件(社会保障番号など含む)
-
LinkedIn:2021年に7億件
-
Google:2016年に100万件
-
Facebook:2019〜2021年に5億件超
2024年には、セキュリティ研究者によって260億件以上のアカウント情報を含む巨大なデータセットが発見されました。これは「MOAB(Mother of All Breaches)」と呼ばれており、中国のメッセージアプリやTwitter、Dropbox、Telegram、Adobeなどのデータが含まれていたと報告されています。
MOABは過去の複数の漏洩事件のデータをまとめたもので、すでに無効になった情報や重複も含まれていますが、桁違いの規模です。
重要なのは、こうした漏洩データがダークウェブなどで日常的に流通しているという点です。つまり、私たちのアカウント情報もすでにどこかで漏れている可能性が高いのです。

自分の情報も漏洩しているかもしれない
「haveibeenpwned」というウェブサイトをご存じでしょうか。メールアドレスを入力するだけで、過去にどの漏洩データセットに自分の情報が含まれていたかを確認できます。
数年以上使っているアドレスであれば、ほぼ確実に「Pwned!(漏洩あり)」と表示されるはずです。
パスワードはどうやって漏洩するのか?
パスワードが流出する主な経路は、フィッシングメールやサイバー攻撃による情報窃取です。これらの手法によって、ログイン情報やアカウントデータベースが丸ごと抜き取られることがあります。
特にクラウドサービスでは、設定ミス(アクセス制限や公開範囲の不備)が原因で、外部からデータが閲覧・取得されるケースも珍しくありません。また、内部関係者による不正行為が原因で起こる情報漏洩もあります。
たとえば2023年にNTT西日本で発生した約900万件の個人情報流出は、委託業者による不正アクセスが発端でした。
また、パスワードそのものが盗まれなくても、推測されやすいパスワードの使用や使い回しによって、不正アクセスのリスクは高まります。人は記憶に頼って多数のパスワードを管理することが難しく、つい簡単で覚えやすい文字列を選びがちです。
たとえば、
-
生年月日や「123456」「password」などの安易なパスワード
-
複数のサービスで同じパスワードの再利用
これらは攻撃者にとって格好の標的です。一度漏洩した情報を用いて、SNSや銀行、ECサイトなどの主要サービスに次々とログインを試みるリスト型攻撃が頻発しています。
パスワード管理の基本対策
パスワードを守るための基本的な対策として、総務省やIPA(情報処理推進機構)、各種セキュリティベンダーが以下のポイントを推奨しています:
-
安易に推測できるパスワードを使わない
-
異なるサービスで同じパスワードを使い回さない
-
パスワードは他人に教えない(家族でも)
-
パスワードマネージャーやOSの保存機能を活用する
-
二要素認証(2FA)を必ず設定する
こうした対策はセキュリティの「基本」ですが、現実には運用が難しい場合もあります。たとえば、「長くて覚えやすく、推測されにくい」パスワードを複数管理しろと言われても、それが難しいからこそ問題になるわけです。
ここで言っている二要素認証(異なる2つ以上の手段を組み合わせて本人確認を行う仕組み)は特に重要な対策です。
パスワードにまつわる俗説の真偽を検証する
● パスワードはメモしてもいい?
PCのモニターに付箋を貼るのはNGですが、紙に書いて厳重に保管するのであれば、むしろ健全な管理方法といえます。パスワードの再利用を避けるためにも、自分用のパスワードリストを作るのは有効です。
ただし、紙を紛失したときのリスクに備え、「一部を伏せ字にする」「略語化する」などの工夫が必要です。WordやExcelなどのファイルで管理する場合も、必ず暗号化を施しましょう。
● 文字種を増やせば安全なのか?
多くのサービスでは、大文字・小文字・数字・記号などを組み合わせることを要求します。もちろんシステムの条件には従うべきですが、実際にパスワードの強度に最も寄与するのは「文字数の長さ」です。
たとえば6文字の複雑なパスワードより、単純でも9文字以上の長さがあるパスワードの方が、**総当たり攻撃(ブルートフォース)**に対する耐性は高くなることがあります。
ただし、あまりに複雑すぎると、自分でも覚えられなくなり、結果的に使い回しやメモへの依存が増えてしまうため注意が必要です。
● パスワードは定期的に変えた方がいい?
かつては有効とされていましたが、現在では無理に定期変更することがリスクにつながるという見解が一般的です。変更を繰り返すうちに、短くて弱いパスワードや、似た文字列での再利用が増えるためです。
ただし、漏洩が疑われた場合にはすぐに変更が必要です。また、複数人で同じアカウントを使用している場合など、運用上の理由で定期変更を設けることは一定の効果があります。
● 秘密の質問は安心なのか?
「母親の旧姓は?」「初めて飼ったペットの名前は?」といった秘密の質問による認証もかつては主流でしたが、現在では十分なセキュリティ対策とは言えません。
SNSの情報から容易に類推できるほか、ひらがな・カタカナ・英語など入力ミスの可能性も高く、いざという時に自分でも思い出せないというケースが多発しています。
ポイント:
重要なのは、人の記憶や運用ルールに依存せず、仕組みやツールを活用することです。
たとえば、ブラウザに内蔵されているパスワードマネージャーは、
-
サイトごとのID・パスワードを安全に保存
-
ランダムで高強度なパスワードを自動生成
-
自動入力によるログインの効率化
など、多くの機能を提供しています。専用のパスワード管理アプリも多く存在し、安全性と利便性を両立する強力な手段となります。
2FA(多要素認証)とデバイス認証は必須機能
パスワードによる認証方式には限界があり、近年ではそれを補完・代替する新しい認証技術の導入が進んでいます。特に重要なのが、次の2つの方法です:
-
多要素認証(2FA / MFA)
-
パスキーや生体情報を用いたデバイス認証
これらは、アカウントのなりすましや不正ログイン、さらにはサーバー侵入といったセキュリティリスクへの有効な対策となるため、積極的な活用が推奨されます。
多要素認証(2FA)
多要素認証とは、異なる2つ以上の手段を組み合わせて本人確認を行う仕組みです。例として、ログイン時に通常のパスワードに加えて、次のような要素を要求するケースがあります:
-
あらかじめ設定した第2パスワード
-
ワンタイムパスワード(OTP) をSMSやメールで送付
-
認証アプリによる認証コードの確認
とりわけSMSやメールによるワンタイムパスワード方式は、攻撃者が仮にログインパスワードを入手していたとしても、利用者のスマートフォンやメールアカウントへのアクセスがなければ突破できません。これにより、なりすましリスクを大幅に軽減できます。
さらに、
-
普段とは異なる端末・環境からのログイン通知
-
アカウント設定変更時の通知
といったアクティビティ監視機能も必ず有効にしておくべきです。万が一不正アクセスが試みられた際、早期に気付いて対応できます。
重要なのは、パスワード単独の認証はもはや安全ではないという前提を持つこと。2FAが利用できないサービスは、相対的にリスクが高いと認識すべきです。
パスキー・生体認証を活用したデバイス認証
現在多くのスマートフォンやPCには、パスコード入力・指紋認証・顔認証といった本人確認機能が搭載されています。これらの機能は、デバイスのロック解除だけでなく、認証手段としての信頼性も高く評価されています。
たとえば:
-
パスキー(PINコード)
-
は、通常4〜6桁の数字ですが、デバイス側で試行回数が制限されているため、総当たり攻撃に対する耐性があります。
-
顔認証では、3Dスキャンや眼球検出を活用し、写真では突破できない精度を実現しています。
加えて、これらの認証情報はすべて端末内の専用領域(セキュアエンクレーブ等)に保管されており、一般的なアプリやインターネットからはアクセスできません。そのため、ネット経由で盗み出されるリスクはほぼ皆無です。
つまり、攻撃者が仮にパスキーの内容を知っていたとしても、対象の端末自体を所持していなければ意味がないのです。
認証アプリ(Authenticator)の活用
2FAをさらに強固にする手段として、Google AuthenticatorやMicrosoft Authenticatorなどの認証アプリの活用も有効です。
この方式では、SMSやメールを介さず、認証済みスマートフォンのアプリにワンタイムパスワードが直接表示されます。これは、
-
通信の傍受やSIMスワップ攻撃
-
メールアカウントへの不正侵入
といった認証コードの横取りリスクを低減します。認証アプリは、デバイス認証と連動するため、アプリをインストールしたスマートフォンを物理的に保持していなければログインできません。
安全なインターネット利用のためのポイント整理
これまでの内容を踏まえ、パスワードとその周辺セキュリティを強化するための要点を以下にまとめます:
-
パスワードを記憶のみに頼らず、管理ツールやメモを適切に使う
-
推測されやすい・短いパスワードは避ける
-
パスワードの使い回しは厳禁
-
パスワードマネージャやブラウザ機能を活用し、複雑なパスワードを生成・管理する
-
2FA(多要素認証)やログイン通知は必ず設定
-
スマートフォンやPCのパスキー・生体認証を活用し、本人以外の利用を制限する
-
認証アプリを利用して、SMS依存のリスクを回避する
パスワード管理は「個人の努力」だけに頼るのではなく、「ツール」と「仕組み」で支える時代です。
これらの対策を積極的に取り入れ、安全なデジタルライフを構築していきましょう。